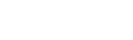聞法するとは聞法の場所へ行ってただ話を聞くことではなく、仏法に遇おうとして私をして家から出させた、その力を自らにたずねることです。本当に大切なことは聞いた法話を覚えることではなく、何が私自身を促し私自身を家から出させたのかをたずねる、そこにこそ私たちの歩みということがあるのです。
安田理深師
梅雨明けを前に夏本番を思わせる暑さが続いています。
今月の常例法座は大阪市光照寺より、本年2月にもご出講いただきました若林眞人先生をご講師にお迎え致します。
16日(火)午後2時よりお勤めの後、ご法話をいただきます。
浄土真宗はお聴聞に極まると申します。どなた様もお誘い合わせの上お聴聞くださいませ。是非ご一緒にお聴聞致しましょう。合掌